
《札幌中高一貫校リスト》


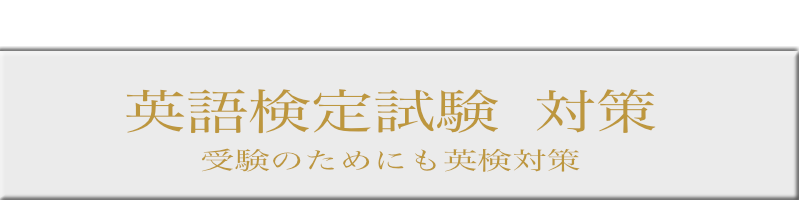





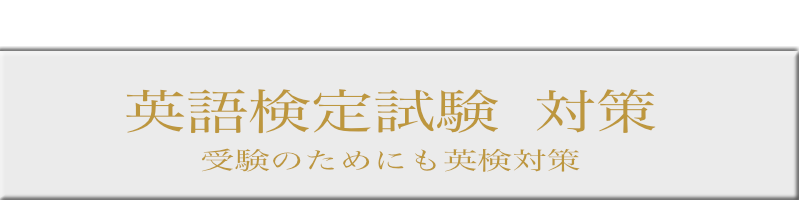





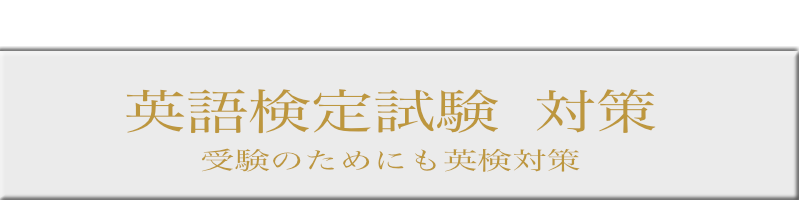





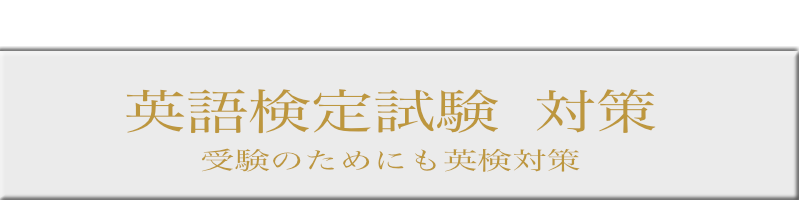





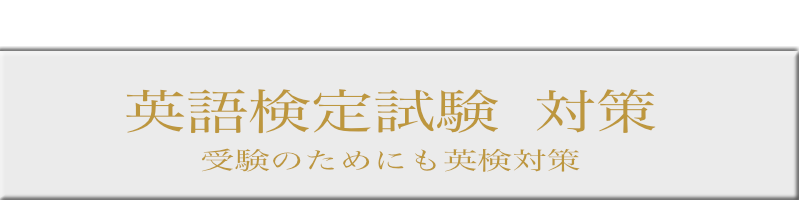





《入試について》
【エデュオからの『札幌開成中等教育』メモ...】

【エデュオからの附属札幌中学メモ】